Renata Pisu 1991年8月22日 La Repubblica
Dipendenza affettiva - 甘え La scimmia giapponese ( 2/2 )
Il termine, come abbiamo già scritto, designa precisamente
l’amore passivo, mentre nessuna lingua europea è in grado di distinguere fra amore attivo e passivo.
Secondo Doi, questa disparità linguistica riflette una diversità nell’organizzazione sociale.
« Amae » sarebbe addirittura il cardine dell’ « ideologia » giapponese, ideologia nel senso di insieme di idee, di concetto dominante che è la base effettiva di un sistema sociale.
Il culto dell’imperatore, per esempio, non sarebbe che una istituzionalizzazione di « amae » in quanto l’imperatore è completamente privo di responsabilità. Come un bambino, cioè,
egli incarna la dipendenza infantile nella sua forma piu pura : è un « amae soddisfatto » : come un bambino, presume che chi gli sta intorno si occupi di ogni cosa, compreso il governo del paese che è una grande famiglia pero senza padri, perché al vertice c’è un bambino e i sudditi sono anche loro bambini in quanto « figli dell’imperatore », condannati pero a vivere le angosce di un
« amae » insoddisfatto.
Ma se questo era vero prima della guerra,nel Giappone tradizionale, con il crollo dell’ideologia del sistema imperiale, cioè dell’ « amae » istituzionalizzato, oggi si ha, per Doi, lo scatenamento di un « amae » senza controllo. Ovunque, nel mondo finanziario come in quello politico, spuntano « piccoli tiranni » vezzeggiati e blanditi da abitudini sociali diffuse, perchè « amae », come ideologia, sarà anche, crollata, ma « i giapponesi non hanno saputo rinnegarla nè estirparla dal profondo del loro cuore ». Per esempio, usare appellativi onorifici, sia quando ci si rivolge ai bambini sia quando si ha a che fare con i superiori, dimostra, secondo Doi, che questi ultimi vanno viziati e assecondati proprio come bambini. Non tanto perchè è meglio tenerseli buoni, ma in quanto il vederli contenti, con il loro « amae » soddisfatto, fa piacere, cioè accontenta anche il proprio « amae ».
Invece, quando ci si sente frustrati, cioè quando A non permette a B di « amaeru », ossia di approfittare della sua indulgenza dando per scontato il rapporto privilegiato esistente tra loro, si cade in stati d’animo che in lingua giapponese vengono sottilmente distinti e che sono tutti riferibili alla pscicologia del bambino : tenere il broncio sapendo pero che è concesso farlo, mostrare la gelosia da chi sa di essere trattato ingiustamente, assumere a
parole atteggiamenti di aperta sfida, fingere la piu totale indifferenza, mostrare risentimenti o odio.Tutti questi termini si riferiscono soltanto a sentimenti provocati dal rifiuto del proprio « amae » e tanta meticolosa precisione lessicale è prova, secondo Doi, dell’importanza fondamentale della sfera di
« amae » in una cultura, come quella giapponese, dove i rapporti umani basati sulla dipendenza si sono integrati nel sistema sociale. Mentre in Occidente ne sono rimasti esclusi, al punto che per gli occidentali è considerato disdicevole la sciare trapelare emozioni di genere « amae », o stabilire rapporti importanti all’« amae », in quanto sono considerati segno di una perdita del controllo emotivo, una regressione.
Ma è chiaro, sostiene Doi, che anche gli occidentali hanno emozioni di tipo « amae » che si notano soltanto se si osserva con occhi giapponesi. Tuttavia, se nel privato anche « amae » e alcuni dei loro atteggiamenti vi si conformano, è nel pubblico, cioè nei rapporti sociali, che lo negano in quanto « amae » è in contraddizione con il principio della libertà individuale che per Doi è uno « splendido articolo di fede dell’Occidente ».
Impossibilità pscicologica della libertàOggi in giapponese-ma d’altronde anche in cinese-il termine che indica « libertà » ha assunto sia il senso positivo occidentale sia quello negativo orientale, il che rende il concetto estremamente ambiguo. E qui Takeo Doi introduce una digressione sulla libertà che, secondo lui, in Occidente non è mai esistita se non come atto di fede,
fede che Marx, Nietzsche e Freud hanno distrutto senza che un nuovo concetto di libertà l’abbia sostituita. Allora perché gli occidentali non dovrebbero riconoscere il valore dell’esperienza giapponese che da sempre insegna l’impossibilità pscicologica della libertà ?
Certo, dice Doi, per i giapponesi non è stato difficile rendersene conto in quanto sono sempre stato in armonia con « amae ». Ma, insinua, non sarà per caso che gli occidentali hanno tutti un « amae » latente ? E, in definitiva, che cosa bisogna farne di questo amae per il quale, come nota Doi « i giapponesi hanno combattuto la guerra del Pacifico in modo da diffondere questa visione del mondo nei paesi d’oltremare » ?
Non c’è risposta in Anatomia della dipendenza, un testo che dice tutto e il contrario di tutto, ma che è di affascinante lettura perché spiega come i giapponesi si vedono - o per lo meno come livede un teorico della scuola dell’Uomo Nipponico- e anche come loro
vorrebbero che fossimo noi : un po piu dolci, un po’ piu consapevoli di « amae ».
レナタピズー記者が書いた中で私が一番印象に残り、とても面白く読んだ記事の一つです。私達には自分達日本人がトロイのは良く解っているのですが、この本で書かれている心理分析をイタリア人読者に解り易くなかなか良く解説してあります。「甘えの構造」の本はよく知られているので、この記事をあえて翻訳しませんが、面白かったのは、この記事がレプブリカ紙に載った後、TVのコントや漫才に沢山利用され、あちこちでこの本の中で書かれている甘えの心理を取り上げて、からかうシーンがぞくぞくイタリアの メディアに出てきました。
人の目を見て話すのが恥ずかしい : スタジオに12歳の男の子を呼び、ジーと司会者の目を見る様に命令して、子供が恥ずかしがるのをカメラがアップで映す。
日本人は12歳 : 以前書いたけど、お笑いコメンター ジャラッパスが MAI DIRE BANZAI で「マッカーサーが日本人は12歳と言ったが、それは間違い120歳です」と使っていた。
口臭が気になる : TV CMによく息を「ハーッ」と吐いて息が臭くないか心配する姿が出回る。
自分が無い : コント等で「ここは何処? 私は誰?」と言う言葉が流行。
丁度湾岸戦争後、でもサダムフセインはまだ健在の状態だった時、「サダム(日本)のおしめを変えに行くのは誰?」とぺローがふざけていた頃です。湾岸戦争で国際社会を味方につける為に米国が総力を出した時期に相変わらず何もしてない風(本当は巨額支援金を出した)な日本(そのわりには世界から憎まれてない)しかたなく出兵した伊も含み当時の参戦諸国のイライラをもろに言い当てていたのが« amae » è amore che tutto perdona,
presunzione di essere amati senza dover far niente per meritarselo, richiesta di un’indulgenza senza fine :
この文章を読んで笑ったのは私だけではなかったみたい。
日本人が子供というのはずーと言われ続けているので、慣れっこになっていますが、湾岸戦争から年月たって、時代の要求から急いで大人になる努力をするかと思えば、今だにその気配がない。昔はキッシンジャーにも「あまりにも幼稚」と言われる始末(そういえば彼2009年4月三極委員会の為に日本に来て金閣寺見物、最後の見納めか、と書かれていた、京都の祇園で遊んだらしい。私には彼が「ハウルの動く城」に出てくる荒野の魔女に見えてしょうがない)
いったい、いつ大人になるのか、無理ならせめて18歳ぐらいにはなって欲しい、甘えから抜け出て、自分で考え、選択して決行する時がきているのに、醜い面ばかり浮き出して、まだまだ独り歩きが出来ない、世界は、日本が鎖国をしたのでまだメンタリテイーの方が追いつかない、国際世界に仲間入りしたのがついこの間、米国から独立して行動するのが怖い、、等々の理由からでは、もう甘えさせてくれない、、
「日本人は12歳」米上院公聴会でのマッカーサー証言からピックアップした多賀敏行氏の調査、産経サイトの「正論」より。
「もしアングロ・サクソンが人間の年齢で、科学や芸術や宗教や文化の面でみて、まあ45歳であるとすれば、ドイツ人も同じくらい成熟していました。しかし日本人は、時間的には古くからいる人々なのですが、指導を受けるべき状況にありました。近代文明の尺度で測れば、われわれが45歳という成熟した年齢であるのに比べると、日本人は言ってみれば 12歳の少年と言ったところでしょう」 (略)
「日本はまだ12歳の少年で、まだ教育可能で、覚えが早くて優等生だ」
http://www.sankei.co.jp/seiron/wnews/0701/ronbun2-3.html









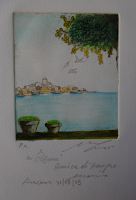
di+mario.png)




 少し神経質だが賢く可愛いい子供や美しい人達が沢山いて見ていてたのもしく勇気が出てくる。パリの日本語補習校には週一回の授業があるが、この学校には金髪で青い目の日本人とのハーフの子供達も日本語を勉強している。もっとも生みの親である日本人の母親は「本当に私の子供かうたぐっちゃうわ、、アハハ」とか冗談を言ったりしてる、、現地校に通う子供が日本語を習うのに通う、このタイプの補習校は世界中にある。
少し神経質だが賢く可愛いい子供や美しい人達が沢山いて見ていてたのもしく勇気が出てくる。パリの日本語補習校には週一回の授業があるが、この学校には金髪で青い目の日本人とのハーフの子供達も日本語を勉強している。もっとも生みの親である日本人の母親は「本当に私の子供かうたぐっちゃうわ、、アハハ」とか冗談を言ったりしてる、、現地校に通う子供が日本語を習うのに通う、このタイプの補習校は世界中にある。
 Roxana Saberi(米国のジャーナリスト、イランと日本のハーフ)
Roxana Saberi(米国のジャーナリスト、イランと日本のハーフ)














